中小企業診断士は「役に立たない・なくなる・廃止される」と言われていた資格の1つです。
理由は、中小企業診断士だからできる「独占業務がない」名称独占資格になっているから。
そして、合格率も中小企業診断士は7%前後と、難しい資格のわりに取得しても使い道がないと言われていました。
しかし、この資格は、国や有識者の後押しなどもあり、2020年から資格取得の難易度が下がり合格率が上がっています。最近では、取得しておいて損のないコスパの良い資格になっているんですね。

中小企業診断士の使い道としては、経営に携わる人が中小企業診断士を取得して実務に活かす、コンサル企業に転職するために取得するのが多いです。
他に独立して研修講師をする、公的機関の業務支援、補助金申請の支援・審査員などがあります。研修講師や補助金関連は副業でも可能だと思います。
また「FP1級、FP2級、不動産鑑定士、行政書士」を持っている方が取得して仕事の幅を広げる人も見かけるので、アイデア次第で幅広く使える資格ともいえますね。

アクセンチュアやボスコン、アビームといったコンサルティングファームに入社してから取得するのは時間の確保が難しいかもしれません。できれば、入社する前か転職前に取得したほうが良いと思います。
中小企業診断士の試験内容
| 試験案内配布・申込受付期間 | 5月上旬~6月上旬 |
| 試験日 | 8月の第3土曜日と日曜日 |
| 合格発表日 | 9月20日前後 |
| 実施地区 | 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の8地区 |
| 受験資格 | 誰でも受験可 |
| 受験手数料 | 13,000円 |
中小企業診断士は、下記の通りです。
1次試験は、8月の土日の2日間を使って行われます。
- 1次試験(選択式7科目):6割以上正解すると合格(8月上旬)
- 2次試験(記述式4科目):6割以上正解すると合格(10月下旬)
- 2次口述試験(面接試験)グループ面接と1人2分程度の受け答え(99%合格できる)
- 実習補修(実習):実習が修了すると中小企業診断士として登録できる
1次試験
各科目は100点満点です。
合格ラインは、全体の60%以上正解すること+1科目でも40点未満がないことです。
| 経済学・経済政策 | 60分 |
| 財務会計 | 60分 |
| 企業経営理論 | 90分 |
| 運営管理 | 90分 |
| 経営法務 | 60分 |
| 経営情報システム | 60分 |
| 中小企業経営、中小企業政策 | 60分 |
2次試験
こちらも各科目100点満点で、合格ラインは全体の60%以上正解すること+1科目でも40点未満がないことです。
| 組織の事例 | 80分 |
| マーケティング・流通の事例 | 80分 |
| 生産・技術の事例 | 80分 |
| 財務会計の事例 | 80分 |
科目が多くて各科目の時間も長いので、合格するには、モチベーションを保つのが鍵になってきます。
2023年 中小企業診断士の合格率と難易度
中小企業診断士の合格者が多い年齢層で一番多いのは50代、次に60代、40代。
資格取得者の仕事は、実際にコンサルファームで働いている人、民間企業に経営計画に携わったり、M&Aなどに従事している人、プロのコンサルとして独立した人などが多いです。


中小企業診断士の合格率は、比較的上昇しています。
| 年度 | 1次受験者数 | 1次合格率 | 2次受験者数 | 2次合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 17,345 | 28.94% | 10,450 | 18.3% |
| 2021年 | 16,057 | 36.40% | 8,757 | 18.3% |
| 2020年 | 11,785 | 42.50% | 6,388 | 18.4% |
1次試験の合格率は2016年の17.7%から上昇傾向、2020年からは36%~40%程度になりましたが、2022年は28%と下がってしまいました。とはいえ、令和以前に比べたら合格率は高くなっています。
2次試験は18%前後で変化はありませんが、2次試験が合否の分かれ目になっています。



難易度が下がった理由は、金融庁の後押しや経済財政諮問会議で新浪剛史議員が中小企業診断士をもっと簡単にしたらどうか?と提言してことにも関係しています。
なぜいま中小企業診断士の難易度が引き下げられるのでしょうか。先の安倍政権は、中小企業の経営基盤を強化するため中小企業政策に力を入れ、ものづくり補助金・事業承継補助金など公的支援を充実させました。その結果、中小企業政策を現場でサポートする中小企業診断士のニーズが増えました。さらに今年は、新型コロナウイルスで苦境に立たされた中小企業を支援するため、各種公的支援のメニュー・予算額が激増しています。
引用:「食えない中小企業診断士」が今後増加する理由
中小企業診断士の制度見直しで変わった点
微妙な感じですが、中小企業診断士の制度について見直しが入りました。
1次試験の一部科目に合格すると「中小企業支援科目合格者」1次試験に合格すると「中小企業診断習得者」と履歴書に書けるようになるというものです。会社の名刺にかけるだけでも、信頼度はアップするかもしれません。
また更新時の対面面接もオンライン対応になるよう進めているそうです。
ITや事業承継など診断士としての強みを伸ばせるようにするため、更新時の対面による実務研修についてオンラインでの実施も検討を進める。
引用:中小企業診断士制度が見直しへ
2023年 中小企業診断士の勉強時間と合格方法
中小企業診断士に合格するには、1000時間と言われていますが、難易度が易しくなってからは、半分以下の勉強時間でも合格できたという人がでてきました。特に、試験が易しかった2020年には、200時間の勉強時間で合格できたという人もいて驚きです・・・。
1次試験は簡単になりましたが、2次試験対策の合格率は特に変動していないので、他受験者と差がつくのは2次試験の対策になるのかなと。この辺は、書籍だけの独学では厳しいと思います。
資格試験の通信講座では、2次試験対策をやっているところもあるので、独学で勉強している人は、2次試験だけ対策の講座を受けるのもアリだと思います。
一部科目の免除制度
申請により試験科目の一部が免除されます。
(1) 科目合格による免除
引用:令和3年度中小企業診断士第1次試験について
(2) 他資格等保有による免除
1次試験の科目で6割をとればその科目は合格となり、以後2年間1次試験では当該科目が免除される制度があります。
(※この制度はデメリットもあり、苦手な科目で高得点をとる必要がでてくるので注意)
2023年 中小企業診断士の通信講座
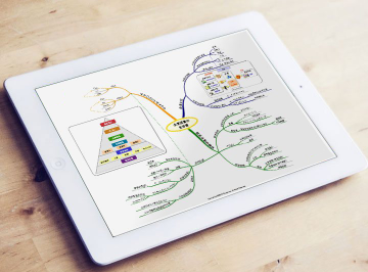
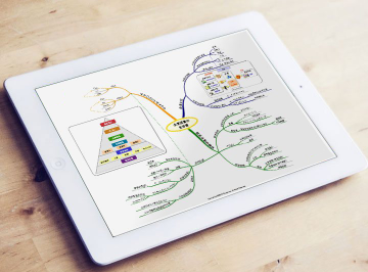
スタディングなどの通信講座を使って中小企業診断士に合格している人はよく見かけます。
この手の通信講座は、大手の通学講座よりも効率良く記憶の定着化ができる仕組みがそろっているので、使っている人が増えていますね。
私もスタディングは、外務員試験で使いましたが、講座が10分~20分程度と短いのでスキマ時間に勉強しやすく、記憶が定着しやすい夜の寝る前にもサクッと勉強できるのが良かったです。
値段もかなり安くなっているので、一発合格を目指すならこういった便利ツールも使うと合格しやすいですし、モチベーションも保ちやすくなりますよ。
あと、中小企業診断士合格の肝になる「2次試験対策」もロジックマップを使っていて、理論的に解答を出せるのは良いなと思いました。さわりを無料体験もできるので、よかったら一度試してみてくださいね。
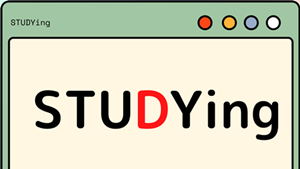
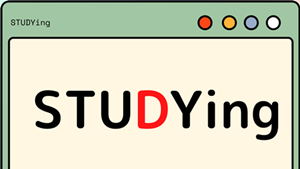
累積 310名
最新令和3年度133名
中小企業診断士の口コミ



学びならちょっと背伸びして流行の国会資格を取ろうとおもい、中小企業診断士に挑戦中。スキマ時間にできるスタディング、無料講座うけてみたけど、よさそうだな。スタンダードコースで55000程度。23年まで受講したとして、ひと月3,000円ちょいの計算
引用:https://twitter.com/



まさか開業するとは1年前は思ってもいませんでした。去年の今頃は中小企業診断士を丸2か月勉強して「もしかしたら7科目間に合うかも」という感じです。企業経営理論、運営管理、財務会計、情報システムの4科目、スタディングの問題を2-3周しただけなんだけど。何故かいけそうかもと思えたんですよね。
引用:https://twitter.com/
中小企業診断士の疑問・FAQ
中小企業診断士の平均報酬はいくらぐらい?
使えないと言われる資格ですが、稼いでいる人は沢山います。


経営コンサルは単価が高く日当5万~10万ぐらいは貰える仕事です。私の知人は、企業のマネジメントとして入って、月に150万~200万で3ヶ月更新契約していました。
優秀な人であれば、マネジメント業務を請け負ったり、経営顧問を数社契約したりと引く手あまたです。(例えば、M&Aのノウハウが豊富、人のマネジメントに強い、マーケティングに強い、生産管理に強い、財務分析が得意などの能力がある)
ただ、実際のコンサル業務は、中小企業診断士を取得したからといって簡単に受注できるような仕事はありません。
基本は、前職のコンサルティングファームで積み上げた取引先から仕事を貰ったり、経営者の集まりに顔を出してコネを作り、仲良くなって仕事をもらうという活動を地道にやっていくのが一般的です。中小企業診断士には独占業務がないので、泥臭い営業でのコネ頼みになります。
会社員でいる間は、会社のブランドを使えますが独立するとそれがなくなるので、独立前にコネを作っておいたほうが独立してからスムーズに営業活動ができます。
QA
中小企業診断士の試験内容とは?
中小企業診断士の試験は、主に3つの科目で構成されています。それは、1) 事業経営と法務、2) 経営分析と診断、3) コンサルティング手法です。これらの科目は、中小企業に関する知識、法律、経営分析、コンサルティング手法などに焦点を当てており、実務に即した内容が含まれています。
中小企業診断士の試験難易度は高いの?
中小企業診断士の試験は、幅広い知識と高度な理解力が求められるため、一般的に難易度は高いと言われています。特に、実務に基づいた問題解決能力や総合的な判断力が必要なため、準備が必要です。
中小企業診断士の試験日は決まっている?
中小企業診断士の試験日は毎年決まっており、通常は6月と11月に実施されます。試験の日程や申込期間などは公式ウェブサイトで確認することができます。
中小企業診断士試験はいつ廃止される予定?
中小企業診断士試験の廃止予定は現時点ではありません。試験は需要があり、中小企業の健全な発展に貢献しているため、今後も継続される見込みです。
中小企業診断士試験の合格率は高い?
中小企業診断士試験の合格率は比較的高くありません。試験は難易度が高いため、しっかりとした準備が必要です。合格率を向上させるためには、十分な勉強と対策が必要です。
中小企業診断士のどの科目が難しいですか?
中小企業診断士の科目の中で、特に難しいとされるのは「経営分析と診断」です。この科目では、企業の経営状況を適切に分析し、問題点を診断する能力が求められます。
中小企業診断士の独学勉強において、非効率的な点は何か?
中小企業診断士の独学勉強において非効率的な点は、適切な情報の収集や勉強計画の立案が不十分な場合です。また、単独での勉強では疑問点の解決が難しいことも挙げられます。
中小企業診断士を独学で一発合格するための勉強法は?
中小企業診断士を独学で一発合格するためには、まず試験範囲を十分に把握し、効果的な勉強計画を立てることが重要です。過去問題の解答や模擬試験を積極的に活用し、自身の弱点を克服する努力が求められます。
中小企業診断士の独学合格に必要な勉強時間の目安は?
中小企業診断士の独学合格に必要な勉強時間の目安は個人差がありますが、一般的には数百時間以上の集中的な勉強が必要です。科目ごとに必要な時間を適切に配分し、定期的な復習を行うことが成功の鍵です。
中小企業診断士の勉強時間はどれくらい必要?
中小企業診断士の勉強時間は個人差がありますが、通常は数百時間から千時間以上が必要です。各科目の内容や自身の理解度に応じて、十分な時間を確保しましょう。
中小企業診断士はどのくらいで取れる?
中小企業診断士の資格を取得する期間は個人によって異なりますが、一般的には数年から数年半程度かかる場合が多いです。勉強の進め方や合格までの努力次第です。
中小企業診断士になるまで何年かかる?
中小企業診断士になるまでの期間は個人差がありますが、通常は数年から数年半程度の準備期間が必要です。試験勉強や実務経験を積みながら、着実に目標に向かって進んでいきます。
中小企業診断士は独学で
受験できますか?
はい、中小企業診断士は独学でも受験することができます。ただし、試験範囲や難易度を十分に理解し、効果的な勉強計画を立てることが重要です。
中小企業診断士の独学での勉強時間は?
中小企業診断士の独学での勉強時間は個人差がありますが、一般的には数百時間以上が必要です。各科目の理解度や勉強ペースに合わせて、適切な時間を確保しましょう。
中小企業診断士の勉強法でおすすめの方法は?
中小企業診断士の勉強法でおすすめの方法は、まず試験範囲を把握し、効果的な勉強計画を立てることです。過去問題の解答や模擬試験を通じて実践力を高め、定期的な復習を行うことも大切です。
中小企業診断士の勉強を独学で行う際に役立つサイトはある?
中小企業診断士の勉強を独学で行う際に役立つサイトとして、公式の試験情報サイトや専門の学習サイトがあります。そこでは試験内容や過去問題、勉強法のアドバイスなどが提供されています。
中小企業診断士を独学で学習するための参考になるブログはある?
中小企業診断士を独学で学習するための参考になるブログとして、合格体験記や勉強法に関する情報を提供しているブログがあります。そこでは他の受験生の経験を参考にすることができます。
中小企業診断士を独学で勉強する際に推奨される勉強時間はどのくらい?
中小企業診断士を独学で勉強する際には、週に数時間から数十時間の勉強を推奨します。個人のスケジュールや目標に合わせて、効率的な勉強時間を確保しましょう。
中小企業診断士の受験資格は何?
中小企業診断士の受験資格は、大学や専門学校などでの学業修了と3年以上の実務経験が必要です。詳細は公式ウェブサイトで確認することができます。
中小企業診断士の試験日は年に何回ありますか?
中小企業診断士の試験日は、通常は年に2回あります。試験は6月と11月に実施されますので、詳細な日程は公式ウェブサイトで確認してください。
中小企業診断士の試験を受ける年齢は?
中小企業診断士の試験を受ける年齢は、18歳以上であれば誰でも受験することができます。年齢に制限はありませんが、一般的には社会人や大学生などが受験します。
中小企業診断士は就活に有利ですか?
中小企業診断士の資格は、経営コンサルティングや経営分析などの職種で就職活動に有利になることがあります。特に中小企業やコンサルティングファームなどでの求人に役立つことがあります。
中小企業診断士の役割は具体的に何?
中小企業診断士の役割は、中小企業の経営を支援することです。具体的には、経営分析や問題解決の支援、経営コンサルティング、経営改善策の提案などが主な業務です。
中小企業診断士に関連する機関はどんなものがある?
中小企業診断士に関連する機関としては、中小企業診断士協会などがあります。これらの機関は、中小企業診断士の資格の運営や普及、研修などを行っています。
中小企業診断士の資格を取得すると何ができるようになる?
中小企業診断士の資格を取得すると、中小企業の経営支援やコンサルティング、経営アドバイスなどの仕事ができるようになります。企業の健全な経営をサポートする専門家として活躍で
きます。
中小企業診断士を独学で学ぶ際の勉強方法について教えてください。
中小企業診断士を独学で学ぶ際の勉強方法は、まず試験範囲を把握し、効果的な勉強計画を立てることが重要です。過去問題や参考書、オンライン学習サイトなどを活用して、効率的に知識を吸収しましょう。
中小企業診断士を独学で合格するための勉強方法は何が効果的?
中小企業診断士を独学で合格するための勉強方法としては、まず試験範囲を把握し、弱点を克服することが重要です。過去問題の解答や模擬試験を通じて実践力を高め、定期的な復習を行うことが効果的です。
中小企業診断士を独学で学習するための参考になるテキストは何?
中小企業診断士を独学で学習するための参考になるテキストとしては、公式の試験対策書や専門の参考書があります。これらの書籍は試験範囲に沿った内容であり、効率的な勉強ができます。
中小企業診断士を独学で学習するための参考になるブログはある?
中小企業診断士を独学で学習するための参考になるブログとしては、合格体験記や勉強法に関する情報を提供しているブログがあります。そこでは他の受験生の経験を参考にすることができます。
中小企業診断士は難しいですか?
中小企業診断士は、幅広い知識と高度な理解力が求められるため、一般的には難しいとされています。特に実務に即した問題解決能力や総合的な判断力が必要とされるため、十分な準備が必要です。
中小企業診断士は必要ですか?
中小企業診断士は、中小企業の経営支援やコンサルティング、経営アドバイスなどの仕事を担う専門家として必要です。企業の健全な経営をサポートし、地域経済の発展に貢献します。
中小企業診断士は誰でも受かりますか?
中小企業診断士の試験は難易度が高く、合格率も比較的低いため、誰でも簡単に受かるわけではありません。しかし、適切な準備や努力を積み重ねれば、誰もが合格する可能性はあります。
中小企業診断士はどんな人が向いていますか?
中小企業診断士に向いているのは、中小企業に興味や関心を持ち、経営支援やコンサルティングなどの仕事に興味を持っている人です。また、経営分析や問題解決能力があるとさらに適しています。
