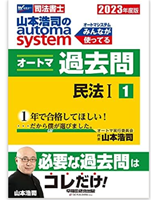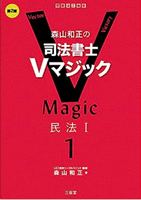司法書士試験は、行政書士を取った方や、司法書士の元で働く司法書士補助者、主婦の方など多くの方が取得している資格です。

難関資格だけあって、一度取ってしまえば一生物で定年後も仕事になるため長期的な目線でみれば持っておいて損はない資格です。
もし資格を取得して司法書士の事務所に勤務する場合は、勉強したわりに稼ぎはそこそこ(年収400万~)なので、現在仕事をしてる方は、その仕事を辞めてまで転職するメリットは低い気がします。
どちらかというと、将来的に独立して自分の司法書士事務所を立ち上げるなど、独立志向が強い方におすすめの資格です。
司法書士事務所のメイン業務は「不動産登記の立会や書類申請・商業登記・140万円以内の任意整理(※認定司法書士のみ)」がありますが、近年の登記立会は、補助者ではなく司法書士が現場に直接赴くことが増えているため以前よりも需要は増えています。就職や転職はしやすい職種だと思います。
認定司法書士は、次のような「簡裁訴訟代理関係業務」を行うことができます。 簡易裁判所において、訴額(請求額)が金140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、あなたに代わって行います。 簡易裁判所において、あなたの代理人※として、少額訴訟債権執行(給料の差押えなど)の申立てを行います。
引用:認定司法書士とは|愛媛県司法書士会
2024年 司法書士試験の難易度と合格率
司法書士試験は合格率4~5%の難関試験です。
平成23年から25年までは、合格率3%程度だったので、合格率はあがっています。1%程度の差でも合格者数でみると100人以上は増えている事になるため以前よりも合格しやすくなっています。
| 年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 16,133人 | 13,372人 | 695人 | 4.31% |
| 令和4年(2022) | 15,693人 | 12,727人 | 660人 | 5.18% |
| 令和3年(2021) | 14,988人 | 11,925人 | 613人 | 5.14% |
| 令和2年(2020) | 14,431人 | 11,494人 | 595人 | 5.17% |
| 平成31年(2019) | 16,811人 | 13,683人 | 601人 | 4.39% |
勉強時間は、一般的に3,000時間以上必要とされています。仕事をしながらだと5,000時間は見ておいたほうが良いです。
一発合格は難しいため最低でも1年半~2年間で合格できるよう計画を立てるのが一般的ですね。
仮に1日3.3時間=毎月100時間コツコツ勉強しても、2年で2400時間の勉強時間にしかならない事を考えると、仕事をしながらの試験勉強がいかに大変かわかると思います。

司法書士試験は相対評価です。合格点が年度によって推移するので、何点以上とれば合格というのはありません。(行政書士試験は絶対評価で180/300点=全体の6割とれば合格できる)
高卒でも取得可能
司法書士は、難易度が高いと言われていますが、学歴などの頭の良さは関係ありません。
例えば、司法試験は、東大や早稲田などの高学歴の人が多く受けているためライバルは強敵ばかりですが、司法書士試験になると合格者層は様々で、30代~40代の主婦の方や仕事をしながらのサラリーマンなど様々だからです。
中には、高校中退や高卒でも取得して独立している人はいます。ただ、高卒の方が司法書士に合格したときは、毎日12時間を2年続けたといっていたので、それぐらいの勉強時間は覚悟したほうがよさそうです。(12時間✕30日✕365日=4320時間✕2年=8640時間😅)
結局、試験が難しいというよりも、多くの人が膨大な出題範囲を見て最後まで勉強を完了できずに受験を諦めてしまうの試験なので、最後まで勉強をやりきる根性さえあれば偏差値は関係なく合格が可能な資格といえます。
司法書士試験のスケジュール
司法書士は、受験資格がありません。社労士だと短大卒と同等の学歴などの受験資格があったので、それに比べると誰でも取得できる資格です。
| 試験日 | 筆記試験、口述試験 |
| 筆記試験合格点 | 令和3年は満点280点中208.5点以上(相対評価なので基準点は年度によって変わる) |
多くの人が1年以上をかけて試験に望みます。
専業で勉強するなら1年~1年半の学習期間、兼業で仕事をしながら勉強する人は2年以上の学習期間が必要とみたほうが良いです。週5日働いている人や主婦で小さい子供がいる人なら、2年の勉強期間をとるのが確実です。
司法書士試験の試験内容
試験の科目は、主要4科目「民法、不動産登記法、商法、商業登記法」で8割ぐらいを占めます。民法のウェイトが高いので、行政書士を取得していて民法を勉強していると多少は勉強しやすいですね。
ただ、司法書士の民法は過去問30年分ぐらいの出題範囲なので行政書士の民法よりも大変です。
残りの2割の出題は、主要4科目以外の7科目(民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法、憲法、刑法)から出ます。こちらはマイナー科目と呼ばれていて全体の2割程度しか試験にでませんし勉強量は少なめです。
主要4科目をいかに攻略するかが鍵になってきます。
択一形式(午前・午後)
午前と午後の択一式があり、午前と午後で基準点があります。
午前は、目安で「26~30問/35問」
午後は、目安で「22~26問/35問」
を超えないと記述式の採点をしてもらえません。
午前試験
| 午前 | |
|---|---|
| 憲法 | 3問 |
| 民法 | 20問 |
| 刑法 | 3問 |
| 商法・会社法 | 9問 |
午後試験
| 午後 | |
|---|---|
| 民事訴訟法 | 5問 |
| 民事執行法 | 1問 |
| 民事保全法 | 1問 |
| 司法書士法 | 1問 |
| 供託法 | 3問 |
| 不動産登記法 | 16問 |
| 商業登記法 | 8問 |
午後記述式
司法書士は、記述式がかなり大事になってきます。
記述式では、問題を紐解いてほぼ白紙の紙を埋める作業があり、数百ある登記の書式を頭に叩き込む必要があります。記述式だけで、全体の勉強の3割ぐらいの時間を費やす必要があるため、午前と同じくらい対策が必要になります。
| 記述式 | |
|---|---|
| 不動産登記法 | 1問 |
| 商業登記法 | 1問 |



試験免除は、2種類あります。1つは、一定年数を公務員として勤務した人は試験免除。前年度の筆記試験合格者は筆記試験だけ免除が可能です。前者は、最場所で働く裁判官の補佐業務をする公務員や簡易裁判所の裁判官に限るので、こちらは一般受験者には難しいですね。他に、法務局で何十年も働いた人も対象になっているようです。
2024年の司法書士試験の通信講座
司法書士試験は、膨大な範囲があるため通信講座や予備校に行ったほうがいいのか?迷いますよね。
中には、独学で合格する人もいますが、勉強スケジュールや要点をすべて自分でやるのは非効率ですし、モチベーションを保つのがかなり難しいです。
実際、司法書士試験の受験勉強を始めたうちの2~3割ぐらいは、途中で挫折して勉強をやめてしまいます。(独学は特に)
それなら、自己投資で20万~40万を払って一発合格を目指すのが賢いやり方だと思います。今は昔と違って、通信講座も料金が安くなったので比較的勉強の土台は作りやすいですよ。
司法書士の通信講座で有名なのは、スタディング、伊藤塾、TAC、LEC、辰巳法律研究所ですね。司法書士の講師数が少ないので有名な先生は限られてきます。
司法書士講座の料金相場
料金の安さなら10万前後で受講できるスタディングがダントツで安いです。スタディングで実際に司法書士に合格している人もいますので、本人の努力次第といった感じです。
他に、大手予備校だと「伊藤塾、TAC、LEC、辰巳」がだいたい40万~60万前後が相場。高額系のところはサポートもしっかりしているので、お金に余裕がある人や、試験勉強の不安が大きい人に向いてます。
特に司法書士は11科目もあって途中で挫折しやすいので、サポートが良いところにしておいたほうが安心です。
各社の司法書士オリエンテーション動画を見てみましたが、伊藤塾の山村拓也先生のガイダンスと声が一番しっくりきました。個人的に聞きやすい声だと1.5~2倍速にしても聞きやすいのでタイパを考えるなら大事だと思います。
何せ司法書士は授業の時間が膨大なので1.5倍速ぐらいでは聞けるようにしたいところです。
塾や通信講座で一番重要なのは、講師が自分に合うかなので、講義の触りぐらいは一度聞いてから選ぶのが良いですね。
司法書士講座の講義時間
講義時間については、講師の話の速度や話し方によっても講義時間は変わってくるので比較対象としては参考になるかわかりませんが、参考に入れてみました。400から500時間が目安です。リアリスティックの松本先生は若干早口なので短めです。
| 司法書士通信講座 | 講義時間の目安 | 料金の目安 |
|---|---|---|
| 伊藤塾 | 400~500時間 | 45万~60万 |
| TAC(山本先生) | 500時間前後 | 45万~60万 |
| リアリスティック | 407時間 30分 | 45万~60万 |
| スタディング | 150時間+記述式27時間 | 99,000円 |
2024年 司法書士の通信講座どこがいい?
伊藤塾 司法書士講座(スタンダード、ステディコース)
伊藤塾は法律系に強い資格塾なので、司法書士の講義は充実しています。
中でもベテラン講師なのが司法書士講師歴15年の山村拓也先生です。行政書士講師の平林勉先生の師匠でもあります。
山村拓也先生の物腰柔らかい喋り方は、どことなく伊藤真塾長に似ていますね。
山村先生は非常に丁寧で無駄のない講義で、解答のプロセスを重視していて理論的です。特に記述の解き方では、「山村メソッド」を確立した第一人者。その安定した解法には定評があります。合格した方の答案を山村先生が出していたのを見ましたが、山村先生の講義通りにほぼ完コピしていました。
受験者の中には、一発合格や6ヶ月で合格した方など上位合格者も多いので、合格体験談などを一度見てみると参考になりますよ。
また、若手エースの高橋先生と宇津木先生の講座もわかりやすいです。特に1回45分の講義というのは画期的。他の予備校の司法書士講座は3時間1コマが多いので、それに比べるとスキマ時間に取り組みやすいのが良いですね。
| 山村拓也講師+高橋 智宏講師 | スリーステップコース | 体系編:18時間 ステップアップ編:111時間 本論編:381時間 +記述演習 |
| 山村 拓也講師 | スタンダードコース | 体系編:18時間 本論編:381時間 +記述演習 |
| 宇津木 卓磨講師 | ステディコース | 講義:247.5時間 演習:択一+記述 |
| 小山晃司講師 | エクシードコース | 講義:219時間 答練+記述+模試 |
スタディング司法書士講座 総合コース
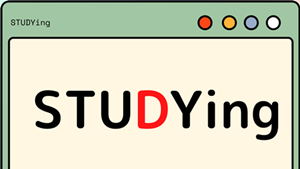
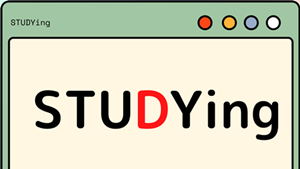
累計16名(合格者の声に掲載数)
最新令和3年度8名(合格者の声に掲載数)
山田先生は、大手資格予備校と通信教育の講師経験もあって教え方が上手です。また、司法書士事務所もやっているので実務的な話も参考になりますね。
全体の講義時間は150時間と一番短いのですが、早めにインプット講義は済ませて、要点暗記ツールで何周も回して覚えていくという感じになります。
実際に司法書士に合格した方の口コミを見ても、暗記ツールを絶賛している人が数名いました。暗記ツールはコンパクトにまとまっているので印刷して書籍代わりにして何周も回すのもおすすめです。
また、スタディングの司法書士講座は、値段が激安なのでオートマやリアリスティックのサブにもぴったりです。スマート問題集は1問1答なので知識の確認や整理などをスキマ時間にやるのに適していますよ。
ただ欠点として、記述式が実用には足りてないので、リアリスティックやオートマの記述式をベースに対策したほうが良いですね。
TAC 入門総合本科生/山本オートマチック
TACは司法書士の顔とも言える山本先生と姫野先生(男性)がいます。
山本先生は、東大法学部出身なので相当頭が良く、司法書士にもわずか6ヶ月で合格しています。
オートマシステムは、非常に読みやすく勉強しやすいテキストで受験の神本とも言われています(ただ誤字脱字は多め・・・)
概要と論点がわかりやすいのでオートマと六法をメインに合格した人も多数いるので立ち読みして見るのもおすすめですよ。
山本先生の講義とテキストは、合う合わないが分かれるので一度体験動画を見てみると良いですね。
姫野先生も、ベテランでわかりやすい先生です。
講義のテンポがよく、個人でやってるyoutubeライブなどでは、歯に衣着せないしゃべりが面白く個人的には好きな先生の一人です。Wセミナー中上級者対象コース「上級総合本科生」の教材も執筆していて初心者からリベンジ組までカバーしています。
個人でもゲリラ的にツイッターでライブ中継をやっているので見てみるのもよいかと。
LEC 9ヶ月合格コース/15ヶ月合格コース
LECは、司法書士3人衆の「海野先生、森山先生、根本先生」のベテラン勢がいます。
海野講師
海野先生は、おかーちゃん的存在で講師歴26年近く。たまに講義で話すエピソードが面白いですw 真田十勇士の海野の家系らしく、豪胆な雰囲気がありますね。
※海野先生は、2022年の12月に体調を崩してしまい講座は募集しておりません。
根本講師
根本先生は面白い先生で、パーフェクトローラーなどを担当。主に択一対策を得意としています。合格ゾーンというシンプルにまとめたテキストも発売しています。
森山浩志
森山先生は、真面目で実直な先生で温厚な方です。Vマジックという書籍を出していて網羅性も高い教科書です。リアリの松本先生の教科書と似ています。講師歴20年以上で、寸劇や語り口調もわかりやすいので、講師陣の中で一番安定感のある先生だと思います。
オートマの山本先生と同様、合う合わないはあると思いますが、数多くの合格者を出しているのは間違いないので、youtubeなどでLECの先生の動画を一通り見てみるのが良いと思います。
クレアール司法書士講座
- クレアールは学習範囲を絞り込んで、短期合格を目指す戸谷満講師の「非常識合格法」を売りにしています。
- 紙とPDFの両方が利用可能で、1年間の講座延長ができる「安心保証プラン」で、万一の不合格にも対応しているのが特徴ですね。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 非常識合格法、オリジナル教材、充実したサポート体制 |
| 講座内容 | 基礎コース、本科コース、論文対策コース |
| 口コミ・評判 | 効率的に学習できる、オリジナル教材が使いやすい、サポートが充実している |
| おすすめの方 | 効率的に学習したい方、オリジナル教材で学習したい方、充実したサポートを受けたい方 |
| 資料請求・無料体験 | 可能 |
| URL | https://www.crear-ac.co.jp/shoshi/ |
参考
- 非常識合格法: 司法書士試験合格に必要な知識を最小限に絞り込んで効率的に学習する方法
- オリジナル教材: 非常識合格法に基づいて作成された教材
- 充実したサポート体制: 質問対応、答練添削、学習進捗管理、モチベーション維持のサポート
アガルート司法書士講座
- 受講相談で学習の悩みを10分程度のオンライン面談で解消できるサポートがあります。
- また、定期的なカウンセリングをオプションで受けられルメリットも。
初心者向けコースを担当するのは浅野勇貴講師。上級向けのコースが人気の高い三枝りょう講師です。
三枝さんは司法書士会でも講師歴が長く、資格スクエアなどの色々な予備校を渡り歩いてきています。
他には、youtubeでよく見かける竹田篤史講師も在籍中です。バランスの取れた講義で講師陣が多いのがアガルートの特徴ですね。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 合格率重視、現役講師による指導、充実したサポート体制 |
| 講座内容 | 2024年、2025年、2026年の合格目標に合わせた入門総合講義・カリキュラム2初学者向けに最短合格を目指すコース 2024年合格目標の演習総合講義・カリキュラム2学習経験者向けに合格レベルまで学力アップを図るコース 記述・答練パック2記述式問題対策に特化したコース |
| 料金 | コースやオプションによって異なる |
| 口コミ・評判 | 合格率が高い、講師の指導がわかりやすい、サポートが充実している |
| おすすめの方 | 合格率重視の方、現役講師による指導を受けたい方、充実したサポートを受けたい方 |
| 資料請求・無料体験 | 可能 |
| URL | https://www.agaroot.jp/shoshi/catalog |
- 合格率重視: 過去5年間の合格率は70%以上
- 現役講師による指導: 司法書士試験の現役講師が指導
- 充実したサポート体制: 質問対応、答練添削、学習進捗管理、モチベーション維持のサポート
小泉司法書士予備校
もともとLECで講師をしていた小泉嘉孝が独立して一人でやっています。
質問掲示板もご自身で回答していて、かなり丁寧に答えています。講義のボリュームも網羅性が高いです。
ただ、残念なのがテキスト。LECのブレークスルーだとよかったのですが、自作のテキストで内容が薄いので、講義を聴きながら説明を自分で書き込んでいく必要があると思います。
金額は、月額制で予備校内のすべての講義を受講可能。月額3,630円(年間最大43,560円)ですべてのカリキュラムを無制限に受講できるという点ですね。10カ月以内で途中解約すると17万のお金がかかってしまうので注意です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 小泉司法書士予備校 |
| 公式サイト | https://shihoshoshi-school.net/ |
特徴
- 月額3,630円で全講座が見放題
- 最低利用期間は10ヶ月
- テキストのPDFダウンロード・印刷が可能
- スマホ・タブレットでの動画視聴が可能
辰己法律研究所
リアリスティックで人気の松本雅典講師、肢別のパーフェクトユニット田端恵子講師、中上級コースの千葉真人講師と実力のある講師がそろっています。
以前は、小玉講師や海老沢講師といった講師陣もいて、横浜、名古屋、福岡、京都などの支店もあったのですが、今は東京と大阪だけになってしまいました。
フォーサイト
フォーサイトのテキストは、昔から見やすくて評判が良いです。フルカラーでまとめられていて、初学者でも複雑な内容を整理しながら理解することができます。
中村篤史講師が担当していて、テキストの執筆も手掛けているのが特徴です。司法書士講座については、まだあまり実績がないのでそこを考慮して受講しましょう。
オンライン木村ゼミ
アメブロでお見かけしたことがあります。
youtubeでも受講生の方が2名でていて割と昔から実績があるゼミのようです。
司法書士試験の独学テキスト
最近はyoutubeやツイッターを見ると司法書士試験に独学で合格したという声も聞きます。
司法書士試験の参考書・問題集も昔にくらべるとかなり充実しているので、これから独学を目指す方は、立ち読みなどで全てに目を通して自分にあうテキストを探していおいたほうが良いです。



どんな良いテキストや予備校でも下記の点には注意したいですね。
・合格には膨大な暗記が必ず必要
・勉強初期から過去問を解くのは必須
・テキストを何回も回して読み込みは必須
・複数教材に手を出すと間に合わない
・間違えた過去問を理解せず何度もやって答えを覚えてしまってる
早稲田セミナー山本浩司のオートマシステムシリーズ
司法書士の勉強したことがある人なら一度は見たことがある山本先生のオートマです。問題集だけやったり、補助的にオートマを使ったりと受験生によって使い方は色々です。
新でるトコ一問一答
オートマの補完として使ってる人が多いです。
オートマ記述式
リアリスティックシリーズ
5ヶ月に司法書士で合格したという経歴を持つ、まだ30代の非常に若い先生です。
勉強法に独自理論があり司法書士に効率的に合格する方法を提唱しています。辰已法律研究所で司法書士の講座もやっていて、講義のさわりをみたのですが記憶の理論がわかりやすいですね。
司法書士5ヶ月合格法は勉強法の面で参考になります。
リアリスティックの本は、民法を含め16冊もあります。途中、民法改正などがあり難航しましたが、2016年から書き始めて令和3年の12月に全巻が出揃って完成していますが、クオリティの高い書籍を16冊まで書き上げて出版したのはすごいことですね。
特に記述式が優れていて、記述対策にリアリスティックを使う人も多いです。
司法書士講師の松本先生の講座はこちらで簡単にまとめました。
同じ辰巳の女性司法書士講師「田端恵子先生」の講座はこちらにまとめました。
司法書士Vマジックシリーズ
LECの森山先生の本です。私はチラ見したことしかないのですが、他の本に比べて図解が多くわかりやすかったです。
講義などを見る限り、森山先生は知識が広くて頭いい方ですね。
デュープロセスシリーズ
オートマの山本先生が司法書士を受験したときに通っていた早稲田セミナーの先生「竹下貴浩先生」の書籍です。
竹下先生は、とても人気のある先生でしたが、2021年で引退したとの噂もあり現在はTACでの講義ページも消えていました。著書としては、デュープロセスや司法書士1問1答合格の肢が発売されています。改訂版は新発売されていました。
具体的な理由は不明ですが、現在60歳を過ぎたので年齢などの事情により講師から引退したのかもしれませんね。
伊藤塾セレクション/必出3300選
問題集では、伊藤塾セレクションと必出3300選も評判が良く使用者も多いです。
勉強時間5000時間のリアル
司法書士試験に合格した12人に、合格に費やしたインタビューをするという動画がありました。
実際は兼業だと4~5回の受験で、勉強時間も5000~7000時間の人が多いので、3000時間で合格できるのはかなり優秀なほうですね。合格にここまでの勉強時間が必要になると、あまりコスパが良い資格とはいえないかもしれませんが、みなさん挫折したり、心を折りながらも合格しているので尊敬します。
司法書士の将来性は相続業務?
司法書士業界は、高齢化が進んでいて20代の合格者はほとんどいません。合格者の年齢も30代から40代に上がっていますし、司法書士の資格を取得してから独立する人も減っているのが現状です。
そんな司法書士の代表業務といえば不動産登記ですが、最近では司法書士の業務の一つだった法人登記を司法書士なしで行えるシステムもでてきています。
GVA法人登記といって、法務局にいかず司法書士に頼まず格安で登記申請ができるというものです。
公式サイト:https://corporate.ai-con.lawyer/



現在は、ゆうぱっくが送られてきて印鑑をする手間はかかりますが、将来、登記の変更で印鑑が不要になればもっと簡単に申請ができるのは確実です。
このシステムを使うと簡単に「会社の住所変更や商号変更、代表取締役の住所変更、本店移転」などができるのでかなり便利なのですが、こういった司法書士泣かせのシステムが増えてくると、将来的に仕事がなくなってしまう可能性もあります。
逆に、司法書士のバブル再来か?といわれているのが2024年から実施される相続登記の義務化です。一般的にあまり知られておらず、罰金も10万程度なのでどの程度必要性に迫られて登記変更を行うかはわかりませんが、以前に司法書士の過払い金バブルもありましたので、こういった需要が来れば飛躍的に稼げる仕事になるかもしれません。
新人司法書士に役立つ書籍はこちらにまとめました。
QA
司法書士試験の合格発表はいつ?
司法書士試験の合格発表は、試験実施後およそ3ヶ月後に行われるのが一般的です。具体的な日程は、年度によって異なるため、法務省や日本司法書士連合会の公式ウェブサイトで確認する必要があります。
司法書士試験の合格基準点
司法書士試験の合格基準点は、試験ごとに異なりますが、全体の成績と各科目の基準点を満たす必要があります。合格基準点は、試験の難易度、受験者の成績分布、及び合格者に求められる最低限の法律知識と実務能力を考慮して設定されます。基準点は公開されることは少なく、具体的な数値よりも全体の成績に対する相対的な評価が重要となります。
司法書士の勉強科目の順番は?
司法書士試験の勉強を始める際は、まず基礎となる法律知識から始めることが推奨されます。一般的な順序としては、民法を最初に学び、その後不動産登記法や商業登記法などの専門科目に進むことが多いです。民法は他の法律分野の基礎となるため、この順序で学習することで理解が深まります。